作品の査定・評価について
角谷一圭の作品を高く評価しております。
もし作品がお手元にございましたらぜひご相談ください。
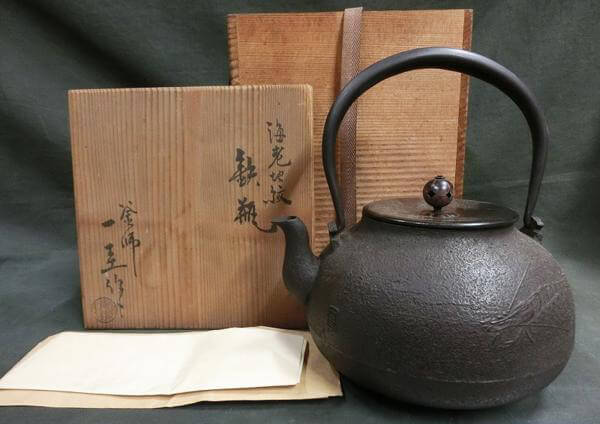 角谷一圭(かくたに いっけい 1904年(明治37年)10月12日‐1999年(平成11年)1月14日)は、日本の釜師。大阪府出身。本名は辰次郎。
角谷一圭(かくたに いっけい 1904年(明治37年)10月12日‐1999年(平成11年)1月14日)は、日本の釜師。大阪府出身。本名は辰次郎。代々宮大工の家計であったが祖父の代から釜作りを開始。釜師の父巳之助から茶の湯釜の制作技法を学び、
1947年(昭和22年)、昭和天皇大阪行幸の際に釜を献上した。
他にも大国藤兵衛、香取秀真から茶釜、鋳金を学び、細見古香庵からは、茶釜を制作するにあたって大きく影響を受けた。
21歳の頃大阪府工芸展に出品した鉄瓶が受賞。本格的に創作活動に打ち込み始める。
終戦直後に出回っていた名釜修理や修復を行い、茶釜の鉄味、形態、地紋などを調査し、鎌倉期の筑前・芦屋釜を模範に和鉄釜を研究した。
1958年、第五回日本伝統工芸展に「海老釜」を出品し高松宮総裁賞を受賞。また1961年の第8回日本伝統工芸展にて「独楽釜」で朝日新聞社賞を受賞した。
1973年、第60回伊勢神宮式年遷宮神宝鏡31面を鋳造(1993年の第61回遷宮の際も制作。)1976年には勲四等瑞宝章を受章した。
1978年国の重要無形文化財「茶の湯釜」保持者として認定される。(人間国宝)
95歳の時逝去。
1904年
大阪府大阪市東成区に生まれる。
1925年
大阪工芸展に初めて鉄瓶を出品し、受賞。
1947年
日展などに初入選。
1958年
第5回日本伝統工芸展に「海老釜」を出品、最優秀の高松宮総裁賞を受賞。
地元である大阪の市や府からも表彰され、布施市文化功労賞や大阪府芸術賞を受賞する。
1961年
第8回日本伝統工芸展で「独楽釜」を出品し、朝日新聞社賞を受賞。
1973年
第60回伊勢神宮式年遷宮に神宝用の白銅鏡31面を鋳造。
1974年
著書『釜師―茶の湯釜のできるまで』を出版。
1976年
勲四等瑞宝章を受章。
1978年
国の重要無形文化財「茶の湯釜」の保持者(人間国宝)に認定される。
1984年
文化庁による工芸技術記録映画『茶の湯釜-角谷一圭のわざ-』が制作・文化遺産オンラインで公開中される。
▶ 文化遺産オンライン|工芸技術記録映画「茶の湯釜-角谷一圭のわざ-」
https://bunka.nii.ac.jp/special_content/movie_stream/52
1993年
伊勢神宮式年遷宮に、「御装束神宝用白銅鏡31面」を鋳造。
1995年
「和銑桜文様透木釜」を伊勢神宮に奉納。
1999年
逝去。
逝去後に従五位に叙せられる。
角谷一圭の代表的な作品
- 「独楽釜」
- 「海老釜」
- 「末広釜」
- 「平丸釜」
- 「馬ノ図真形釜」




